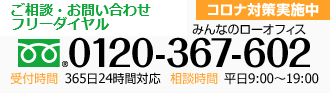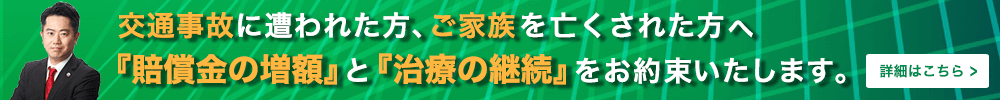【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例
| 依頼者属性 | 性別 | 男性 |
|---|---|---|
| 年代 | 40代 | |
| 職業 | 会社員 | |
| 事故態様と相談 | 事故状況 | 交差点で左折するために停車中に,後続のトラックに追突される |
| 相談のタイミング | 交通事故から約5か月後 | |
| 相談のきっかけ | 後遺障害のことと保険会社との示談の進め方について | |
| 怪我と後遺障害 | 傷病名 | 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫 |
| 自覚症状 | 腰椎捻挫 | |
| 後遺障害 | 14級9号 | |
| 獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
| 金額 | 約358万円 |
1. 事故発生
2. 相談・依頼のきっかけ
依頼者は,交通事故から約5か月間通院治療を続けていましたが,腰椎捻挫について自覚症状が取れないので後遺障害のことについて聞きたいということと,保険会社との示談をどう進めればいいのかを聞きたいということで問い合わせをいただきました。
自覚症状の推移・治療内容・通院状況などからして,後遺障害の等級認定がなされる可能性があると考え,適正な等級認定を受けるために症状固定前からのサポートが必要であると考え受任しました。
3. 当事務所の活動
(1)治療費の立替払いの交渉
受任の時点で事故から5か月以上経過していましたので,加害者の任意保険会社との間で立替払いの継続について交渉をし,事故から6か月目以降も治療費の立替払いは継続することになりました。
(2)症状固定時期の決定
依頼者は,事故から6か月目以降も通院治療を続けましたが,自覚症状についての改善がみられないことから,主治医の意見も踏まえ,事故から7か月を経過した時点で症状固定とし,後遺障害診断を受けることにしました。
(3)後遺障害診断(主治医への手紙の送付)
主治医による後遺障害診断に先立ち,弁護士が主治医宛てに文書を作成して送付し,自賠責の等級認定の判断のために必要な検査を行っていただくようにお願いをしました。
主治医は,必要な検査を行ってくれ,自覚症状・神経学的検査結果・画像所見などがとても丁寧に記載された後遺障害診断書を作成してくれました。
(4)被害者請求
後遺障害診断書を入手した後,任意保険会社を通じて自賠責事務所に等級についての認定を受ける事前認定ではなく,被害者が自賠責に直接支払請求する被害者請求という方法により,当事務所が被害者を代理して自賠責に対して後遺障害についての保険金の請求をしました。
その結果,腰椎捻挫による腰痛・右大腿痛の後遺症につき,14級9号の後遺障害等級が認定されました。
(5)示談交渉
当初から弁護士による示談交渉であったため,初回の提示からほぼ裁判所基準に近い金額での提示でしたが,しかし,裁判所基準での上限額には,若干足りない金額でした(すなわち,逸失利益算定のための労働能力喪失期間が4年(裁判所基準での上限は5年)である点と,入通院慰謝料を通院期間7か月として計算(本件は,8か月として計算することもできる事案であった。)。したがって,さらなる増額を求めて交渉を継続しました。
交渉を継続した結果,労働能力喪失期間については,裁判所基準の上限である5年による算定(約21万円増額),入通院慰謝料については,被害者に有利な8か月間による算定(6万円増額)での賠償を得ることができました。
4. 当事務所が関与した結果
交渉の結果,慰謝料・逸失利益などにつき裁判所基準で示談をし,以下のとおり,約358万円の賠償金を得ることができました。
| 損害費目 | 金額 |
| 休業損害(未払分) | 約37万円 |
| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 108万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |
| 逸失利益 | 約119万円 |
| 損害合計金額 | 約358万円 |
5. 解決のポイント(所感)
当事務所では,案件のほとんどが交通事故の案件であり,その中でも,腰椎捻挫・頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)の相談がとても多いです。むち打ちでの後遺障害の等級は,12級13号か14級9号か,あるいは非該当です。12級13号と14級9号は,画像所見などの多角的所見の有無である程度明確に区別できるのですが,14級9号と非該当では,ともに,はっきりとした多角的所見がないケースなので,その区別は12級13号と14級9号の区別に比べて不明確です。
結局,14級9号か非該当かは,受傷状況・治療内容・通院状況・自覚症状の推移などを総合的に勘案して判断することになるので,症状固定前から適切な治療を受ける,自覚症状については正確に伝える,適切な時期に症状固定をする,後遺障害診断書を適切に正確に作成してもらうといったことを行うが必要です。これらのことを怠ると,自覚症状について適切な等級認定を受けることができずに,残存した後遺症についての賠償金は0円という結果になってしまいます。症状固定前から相談に来た依頼者の方には,適切な等級認定を受けるという観点からもサポートをすることができますので,できるだけ早く相談にお越しいただくのが良いです。
- 【解決事例/080】単身者であったが家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース(後遺障害 併合7級)
- 【解決事例/079】脊柱変形で6級5号の後遺障害が認定された被害者について、交渉段階では賠償金0円の提示であったが、民事調停を申立てたことで約340万円の賠償を得ることができた事例
- 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。
- 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件
- 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例
- 【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例
- 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース
- 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例
- 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース
- 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース
- 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース
- 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース
- 【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案
- 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース
- 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案
- 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案
- 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例
- 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例
- 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例
- 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例