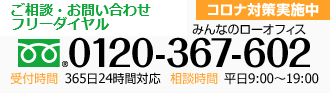損害の請求についてのよくある質問
質問をクリックすると詳細が表示されます
-
交通事故に遭って負傷し、治療のために入院(通院)をしました。この場合、治療関係費や通院交通費などに加えて、慰謝料を請求することは可能でしょうか。
交通事故で負傷し、入院・通院した場合、被害者の方は、「傷害(入通院)慰謝料」を請求することができます。「傷害(入通院)慰謝料」は、治療費などとは別に、怪我したこと自体や入院・通院せざるを得なかったという苦痛(精神的損害)を賠償するためのものです。
慰謝料の算定は、入院・通院の期間を基礎に、怪我の程度も踏まえつつ決定しますが、その金額は一定の基準によって類型化されています。ここで、基準としては、慰謝料の金額が低くなりやすい順番に、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準(弁護士基準)」の3種類があります。
①「自賠責保険基準」 自賠責保険が定めるものであり、3つの基準の中では、慰謝料の金額が1番小さくなります(1日当たり4300円)。自賠責保険が最低限の補償を目的とする強制保険であるからです。
②「任意保険基準」 各任意保険会社が独自に定める基準で、慰謝料の金額は保険会社ごとに異なりますが、「自賠責保険基準」より少し高い傾向にあります
③「裁判所基準(弁護士基準)」 これまでの交通事故裁判例での慰謝料を基にして作成された基準で、3つの基準の中では、慰謝料の金額が一番高くなると考えられます。交通事故被害者としては、裁判所基準が望ましいといえます。
しかし、これ自体に法的な拘束力がないため、自賠責保険や任意保険会社との交渉で、直ちに裁判所基準が用いられるわけではありません。裁判所基準を用いるには、弁護士が保険会社との交渉に入ったり、(交渉でうまくいかない場合には)弁護士が裁判の中で、論理的な主張をしたり、適切な証拠を提出したりして、裁判所を納得させたりする必要があります 。 -
「裁判所基準(弁護士基準)」で慰謝料を算定する場合、病院や整骨院に実際に通院した実通院日数は、慰謝料の算定に全く関係がないのですか?
「裁判所基準(弁護士基準)」の慰謝料の算定は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』の別表Ⅰ・別表Ⅱを用いることになります。基本的には、「負傷の程度」に応じて、別表Ⅰと別表Ⅱ(むち打ち症や、軽微な打撲・挫創など)を使い分け、「入院と通院に要した期間(月単位)」を基に算定します。
しかし、通院が長期にわたる場合、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、別表Ⅰの場合には「実通院日数の3.5倍程度」を、別表Ⅱの場合には「実通院日数の3倍程度」をそれぞれ慰謝料算定のための目安とする場合があります。そのため、通院が長期間に及んだ場合、慰謝料算定にあたって「実通院日数」が全く関係ない訳ではありません。
たとえば、症状や治療内容に照らして、治療が不相当に長期にわたっていると判断された場合 には、(原則の「入院・通院期間」に基づく算定ではなく、)「実通院日数」で慰謝料を算定される可能性があります。 -
先日交通事故に遭い、加害者はひき逃げをしました。ひき逃げを理由に損害賠償額が上がることはありますか。
ひき逃げによる救護義務違反は、「加害者に故意若しくは重過失がある場合」や「著しく不誠実な態度がある場合」として、慰謝料の増額事由に当たり、結果的に慰謝料が増額されることがあります。
ひき逃げによる救護義務違反が認められ、慰謝料が増額された裁判例として、①加害者が被害者に対し、「当たり屋だな」と繰り返し言ったり、加害者が現場から立ち去ったりしたという事案で、通院7カ月の慰謝料(85万円)に20万円を増額した105万円の通院慰謝料を認めています(名古屋地判令和3年7月21日 )。 -
先日交通事故に遭ったのですが、加害者は飲酒運転をしていました。飲酒運転であったことから、損害賠償額が上がることはありますか。
加害者が飲酒運転であったことは、「加害者に故意若しくは重過失」があるとして、慰謝料が増額される可能性があります。裁判例としては、①飲酒した状態で法定速度から46km/時を超過する速度で運転し、被害者に後遺障害14級9号(通院5か月程度)相当の負傷をさせた事案で、通院慰謝料150万円、後遺障害慰謝料132万円が認められています(さいたま地判令和5年3月23日)。5か月の通院期間の場合、通常の通院慰謝料は裁判基準で105万円程度であることから、45万円ほどの増額が認められています。また、後遺障害等級14級認定の場合、通常の後遺障害慰謝料は110万円であることから、22万円程度の増額が認められていることになります。
また、仮に被害者にも落ち度(過失)があり、過失割合が問題となる場合であっても、飲酒運転自体が重過失であるとして、加害者の過失割合が高くなる(結果的に被害者の過失割合が低くなる)ことが考えられます。 -
先日交通事故に遭ったのですが、加害者の事故後の対応や発言が不誠実で、とても納得できません。相手方の不誠実さを理由に損害賠償額が上がることはありますか。
交通事故被害者の方は、加害者に対して慰謝料(交通事故に起因する精神的損害の賠償金)を請求することができます。そして、加害者に著しく不誠実な態度等がある場合には、それ自体が慰謝料の増額事由に当たり、損害賠償額が結果的に高くなることがあります。
このような増額が認められた裁判例として、以下のようなものがあります。
①加害者の一方的かつ重大な過失により、被害者(大学生)を死亡させた事案で、事故後逃走し、逮捕後も完全黙秘し、刑事裁判でも「事故は被害者の速度違反によるものである」旨延べ、被害弁償や謝罪の言葉もなかったことから、3000万円の慰謝料を認めた(東京地判平成15年5月12日 )。 ②加害者の著しい前方不注視で事故が発生した事案で、加害者は事故現場から逃走し、証拠隠滅のために破損したナンバープレートを捨てるなどし、実刑判決を受けて服役後も損害賠償に応じなかったことから、被害者本人分2200万円、妻400万円、子3人それぞれ100万円、合計2900万円の慰謝料を認めた(名古屋地判平成22年2月5日 )。
③加害者が追突事故を起こし、被害者が頚椎捻挫で4か月の通院を要した事案(後遺障害なし)で、加害者が無過失を主張し、信用できない解析を提出するなどして、紛争解決までの期間が著しく長期化したとして、80万円の慰謝料を認めた(東京地判平成14年9月26日 )。 -
交通事故に遭い、介護がなければ生活できない状態になりました。加害者(保険会社)に対して、介護費用などを請求することはできますか。この場合、賠償額はどのように算定されますか。
交通事故によって、ご親族の方に後遺障害(基本的には要介護1級・2級)が残存し、将来にわたって介護が必要となった場合、加害者(の保険会社)に対して、「将来の介護費用」の賠償を請求することが可能です。要介護1級は「常に介護を要する」場合(生活全般において介護が必要な状態)に、要介護2級は「随時介護を要する」場合(排せつや食事などの一部の動作に介護・看視などが必要な状態)に、それぞれ認定されます。
「将来の介護費用」の金額は、在宅介護か施設介護か、(在宅介護の場合)職業付添人がいるか近親者のみか、常時介護か随時介護かなどによって異なります。
施設介護や職業付添人がいる場合、必要かつ相当な実費といえれば、その費用を将来の介護費用とすることができます。一方で、近親者による付添を前提とする在宅介護の場合、要介護1級であれば1日当たり8000~1万円、要介護2級であれば1日当たり5000~8000円ほどが将来の介護費用として認められることが多いと考えられます。ただし、介護の実態によっては、金額が前後することもあります。 -
母が交通事故で重傷を負い、要介護の状態になりました。事故前に住んでいた自宅に戻るには、バリアフリーなどの改修工事が必要です。この自宅改修費用を保険会社に請求することはできますか?
交通事故によって、要介護状態になり、自宅に居住するのにリフォームが必要となった場合、その費用を請求できる場合があります。具体的には、車いすが通ることのできる間取りに変更したり、会談をスロープやエレベーターに変更したりすることなどです。
ただし、介護費用は、その必要性と相当性が認められる場合に限って、賠償の対象となります。そのため、スロープ設置で足りるにもかかわらず、莫大な費用がかかるエレベーターを設置した場合、スロープ設置費用を超える部分は自己負担となる恐れがあります。相手方に請求しようとする考える介護費用が「必要かつ相当」といえるか否かは、難しい判断となります。また、介護費用の金額が大きくなりやすい性質上、相手方も争ってくることが想定されるので、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。