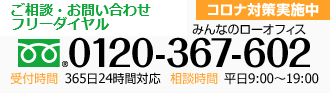休業損害についてのよくある質問
質問をクリックすると詳細が表示されます
-
交通事故では兼業主婦の休業損害はどう扱われるのですか?
兼業の収入と女性平均賃金を比較して高額な方を基準に算定することが多いです。
1 主婦の休業損害
収入を得ていない専業主婦(=家族のために家事をしている人)にも,「休業損害」が発生して,それは女性平均賃金をもとに計算するのが原則です
では,家事もしているし,仕事もしているという「兼業主婦」の休業損害はどうやって計算するのでしょうか。結論から言うと,「兼業による収入」と「家事労働の評価=女性平均賃金分」を比較して,高い方を兼業主婦の日額収入と考えるのが裁判実務です。
家事と労働を行っているのだから,「家事労働と兼業による収入を合計した金額」を日額にするという考えもありましたが,少数説です。
兼業をしている以上,家事も専業主婦と全く同様にはできないはずであるとの考え方から,「どちらか高い方」を採用する考え方が主流です。2 兼業主婦の休業損害の現状
上記した,女性平均賃金とは,例えば平成26年では,年額364万円程度です。
兼業主婦の多くはパート・アルバイトですから,年額364万円の収入を得る兼業主婦は圧倒的少数です。
したがって,兼業主婦の休業損害は,女性平均賃金=年額350万円をもとに算定されることが多数となります。
しかし,保険会社の中には,「兼業主婦の休業損害は兼業と家事分の,高い方を採用する」ということを教えてくれないこともあります。
ですから,保険会社は,兼業主婦の休業損害を,実際の収入をもとに,低い金額で提示してくることがあるのです。
したがって,保険会社の休業損害の算定は,計算式をよく確認する必要があります。
自分の休業損害の算定に疑問を持った方は,弁護士に相談してみましょう。
関連リンク
-
会社員の休業損害は、どのようにして請求すれば良いのでしょうか?
会社員の方が休業損害を請求するにあたっては、①休業損害証明書、②事故前年分の源泉徴収票をご準備していただくことになります。
①「休業損害証明書」は、被害者(会社員)が保険会社や法律事務所から書式を取り寄せた上で、勤務先に「休業日数」、「被害者の事故直近(3か月)の給与額」、「休業日」などを記載してもらいます。
②「源泉徴収票」は、事故前年の1年分に勤務先から支払われた給与等の金額と、被害者が支払った所得税の金額が記載された書類です。被害者が実際に就労していることを確認するために提出が必要となります。
上記①②の書類がそろった場合には、加害者の保険会社にこれを提出します。その記載内容に問題がなければ、休業損害としてその賠償を受けることができます。 -
私は会社で働いているのですが正社員ではありません。交通事故に遭って、しばらく会社を休まざるを得なかったのですが、正社員でなくても休業損害の賠償を求めることはできるのでしょうか。
正社員でない方も、休業損害を請求することができます。
請求の仕方は、正社員の方と同様に、①勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらい、これと併せて②「源泉徴収票」を加害者側の保険会社に提出しましょう。①は事故前の欠勤日を確認するため、②は事故前の基礎収入を確認するための書類です。詳しくは、【69】をご参照ください。 -
休業損害の請求をするための資料として、事故前年の源泉徴収票が必要と聞きました。私は、最近、転職したばかりで、事故前年の源泉徴収票は、現在の勤務先とは違う会社です。この場合、休業損害を請求するために、どのような資料が必要でしょうか。
基本的に、会社員の休業損害請求の資料として「事故前年の源泉徴収票」が要求されるのは、事故当時に勤務している会社での収入を確認する必要があるからです。
そのため、「事故当時の基礎収入を確認できる書類」が必要になります。
具体的には、事故当時、既に転職していた場合、「(現在の勤務先での)事故前3か月間の賃金台帳の写し」や「(現在の勤務先との)雇用契約書」などを提出することで、事故当時の収入を証明することができます。
「現在の勤務先での(事故前年の)源泉徴収票」がない場合でも、あきらめずに代わりとなる書類を集めて、休業損害を請求する準備をしましょう。 -
私は会社員なのですが、交通事故に遭い、しばらく会社を休まざるを得ませんでした。そして、私は近々会社を退職する予定なのですが、加害者に対して休業損害の賠償を求めるのに影響は出るでしょうか。
交通事故に遭った当時に勤めていた会社を退職することになった場合でも、休業損害を請求することはできます。
会社に勤務していた方が休業損害を請求するにあたっては、①「休業損害証明書」、②「事故前年分の源泉徴収票」が必要となります。
①「休業損害証明書」は、事故直近(3か月間)の収入や、休業日数、有給休暇の使用日数などを勤務先に記載してもらう書類です。
なお、 勤務先が「休業損害証明書」の作成を拒むケースがあります。この場合には、この書類を作成しても会社側にデメリットがないことを説明し、作成してもらえるように依頼しましょう。それでも会社が作成を拒む場合には、給与明細やタイムカードなどといった「給与額」や「欠勤日」を把握できる資料を準備しましょう。
②「事故前年分の源泉徴収票」は、会社員としての収入を証明するために必要になります。これらの書面は、当該勤務先(会社)を退職した場合でも入手可能です。なお、退職後に源泉徴収票が送られてこない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで、会社が源泉徴収票を送付することが多いです 。 -
交通事故でケガをして会社を休みました。休んだ期間、健康保険の傷病手当を受給しました。傷病手当を受給すると、保険会社に休業損害の請求をすることができなくなりますか?
傷病手当を受給した場合、傷病手当では損害を補填できない部分を除き 、保険会社に休業損害の請求できなくなります。
「傷病手当」とは、業務外の事由(原因)による病気や怪我の療養のために休業し、仕事に就くことができず、その期間の給与が支払われていない場合に、健康保険から支給される手当金のことをいいます(健康保険法99条)。傷害手当の支給額は、「直近1年間の標準報酬月額を平均した額の30分の1」×「3分の2」×「支給日数」で算出されます。ただし、支給される期間は、支給開始日から最大1年6か月とされています。なお、「標準報酬月額」とは、健康保険料を計算する際に用いる1か月ごとの給与の区分のことをいいます 。
交通事故によって負った傷病により、休業せざるを得なかった場合、これによって生じた損害を補填する方法としては、①上記の「傷病手当」を受給する方法と、②加害者側(の保険会社)に対して休業損害を請求する方法が考えられます。健康保険に加入されている方やそのご家族は、いずれの手段を選択することもできますが、両方の手段を採って、二重に傷病手当と休業損害を受け取ることはできません。傷病手当を受け取ることで、その手当金は既払金として損益相殺の対象となり、休業損害から控除される(差し引かれる)からです。
ただし、①「傷病手当」を受給する方法を選択したものの、その手当金だけでは損害を補てんできない(補えない)場合も考えられます。この場合には、「その不足額」を加害者側に請求することが可能です。 -
自営業の休業損害を請求するにあたり、どのような資料を準備する必要がありますか?
自営業者(事業所得者)の方が、休業損害を請求する場合、①「確定申告書」と②「収支内訳書」又は「青色申告決済書」が必要となります。
①「確定申告書」が必要となるのは、事業所得者の休業損害額の算定に当たっては、事故前年の所得税確定申告所得が基準となるからです。
また、②「収支内訳書」は白色申告者が税務署に提出する書類であり、「青色申告決算書」は青色申告者が税務署に提出する書類です。そのため、それぞれの確定申告の方法に合致した書類を準備しましょう。
これらの書類がない場合、別途「事故当時の基礎収入を立証できる証拠」を準備する必要があります。具体的には、通帳や帳簿、領収書などから基礎収入を証明することが考えられます。また、この基礎収入の立証に際して、「賃金センサス(年齢・男女別の平均賃金)」を用いることがあります。
ただし、そもそも確定申告をしていない場合や、申告漏れの収入は、公的な収入の証明がなされていないため、保険会社は基本的に休業損害の支払に応じません。また、裁判所も、申告をしていないことを重く見るため、簡単には休業損害を認めません。
そのため、確定申告していない収入も含めて休業損害を請求する場合には、その収入の立証がとても重要になります。確定申告をしていない収入がある場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください 。 -
自営業をしていますが、交通事故のために、店舗を休業せざるを得ませんでした。店舗を休業していた間の家賃などの固定費を請求することはできますか?
交通事故により自営業を休業せざるを得なかった場合に、その期間に発生した「固定費」は、「休業損害」として、加害者側(の保険会社)に対して請求することができます。固定費(租税公課や家賃、減価償却費など)は、休業していても発生してしまうものであり、被害者(自営業者)が交通事故によって休業したとしても支払わざるを得ないからです。
自営業者が、休業損害を加害者側に請求する場合、その損害額は、「基礎収入」×「休業日数」で算出されます。このうち、「基礎収入」は、基本的に、「(事故前年の確定申告所得額+固定費)×被害者の寄与率÷365(日)」で計算します。
なお、「寄与率」は、被害者の稼働がその事業での利益にどれほど寄与しているか(役立っているか)という割合です。被害者本人の休業により、事業も完全にストップするのであれば、100%ということになります。 -
私は自営業者なのですが、交通事故に遭い、しばらく仕事を休まざるを得ませんでした。休業損害の賠償を求めようとしたのですが、加害者側の保険会社から「確定申告がなされていない以上、休業損害の賠償には応じられない」と主張されました。自営業者が休業損害の賠償を求めるにあたっては、「確定申告」が必要不可欠なのでしょうか。
確定申告をしていない場合でも、休業損害を加害者側の保険会社に請求することは不可能ではありません。しかし、確定申告を適切に行っている場合と比較すると、その難易度はかなり高くなります。
「休業損害」とは、交通事故で負った怪我や病気により、自営業を休まざるを得なくなった場合に、その休業によって発生した損害のことをいいます。例えば、交通故事により、入院を余儀なくされた方が、一人で飲食店を営んでいた場合、その入院期間などは店を開けることができず、その間に得られたはずの利益を得られなくなっていることから、「得られたはずの利益」を損害として、加害者側の保険会社に請求することができます 。
損害額は、「基礎収入(事故当時の1日当たりの収入)」×「休業日数」で求めることができます。そして、自営業者の「基礎収入」を算出するには、基本的に①「確定申告書」と、②「(青色申告者の方は)青色申告決算書」、又は「(白色申告者の方は)収支内訳書」を準備する必要があります。これらの書類があれば、「事故当時の収入」を公的に証明することができ、基礎収入を算出しやすくなります。
もっとも、確定申告をしておらず、①②の書類がない方でも、他に「事故当時の収入」を証明できる証拠があれば、「基礎収入」を立証できる場合があります。証拠となりうるものとしては、通帳や帳簿、領収書などが考えられます。
ただし、ここで立証しようとする収入は、「本来確定申告をしなければならないにもかかわらず、確定申告をしなかった収入」です。そのため、加害者側の保険会社は、基本的にその収入を否定して、保険金を支払わない対応を採ります。また、裁判所も、確定申告をしていなかったことを重く見るため、その休業損害は認められづらいといえます。そのため、確定申告をしていない収入については、その収入の立証の難易度が高く、専門的知識が重要になります。もし確定申告をしなかった収入がある場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 -
自賠責保険では、自営業者の休業損害は、どのように支払われますか?
休業損害の損害額は、「基礎収入(1日当たりの収入)」×「休業日数」で計算します。もっとも、自賠責保険における休業損害の計算では、基本的に「基礎収入」を日額6100円とします。ここでいう「6100円」については、実際の収入の疎明(立証) がない場合でも支払われます。そのため、基礎収入が6100円以下の方であっても、6100円を基準として、休業損害の賠償を請求することができます。
逆に基礎収入が6100円以上の方は、その収入を立証して、「1日につき6100円を超えることが明らか」となれば、「1日当たり1万9000円」が上限として、実際の基礎収入を基に、休業損害を請求することができます。
ただし、自賠責保険には、「賠償金合計額」に上限が設けられています。たとえば、「傷害による損害」については、治療費や慰謝料、休業損害などの賠償金は「120万円」までしか支払われないとされています。そのため、自賠責保険だけでは、トータルの損害額を補い切れない恐れがあります。 -
交通事故による自営業の減収を立証できなかった場合は、休業損害は全く支払われないのでしょうか?
「休業損害」とは、交通事故で負った怪我や病気により、自営業を休まざるを得なかった場合に、休業したことによる収入の減少分のことをいいます。そのため、自営業者の方は、原則として、①「確定申告書」と、②「(青色申告者の方は)青色申告決算書」、又は「(白色申告者の方は)収支内訳書」を提出することで、収入の減少を立証することができ、休業損害を請求することができます。
もっとも、確定申告書などの公的書類がない場合でも、その代わりに「事故当時の収入」を立証できる証拠を用いて、収入の減少を立証することも可能です。具体的には、入出金を把握できる「通帳」や、売上・経費を把握できる「領収書」、「帳簿」などから「事故当時の収入」を立証することができる可能性があります。 -
私は専業主婦なのですが、交通事故に遭い、治療のため、しばらく家事をすることができませんでした。「専業主婦」は休業損害の賠償を求めることができるでしょうか。
主婦(主夫の方も含み、性別は問いません。)の方などのいわゆる「家事従事者」が、交通事故で負った怪我や病気によって、家事に従事できなくなった場合、休業損害を請求することができます。家事労働では現実に収入を得られないものの、その労働は経済的に評価できるものであるからです。
休業損害は、「基礎収入(1日当たりの収入)」×「休業日数」で算定します。家事従事者の基礎収入には、基本的に「全年齢の女性の平均賃金」を用います(主夫の場合も、この平均賃金を用います)。もっとも、被害者の年齢や身体状況に照らし、基礎収入が「全年齢の女性の平均賃金」を下回る場合があります。
なお、仕事も行いながら家事労働にも従事する「兼業主婦(主夫)」については、「実際の収入」と「全年齢の女性の平均賃金」を比較して、いずれか高い方が基礎収入となります(二重で請求することはできません。)。 -
私は兼業主婦で、家事とパートをしていますが、交通事故に遭ったためしばらく家事とパートをすることができませんでした。「兼業主婦(主夫)」は、家事と仕事両方の休業損害の賠償を求めることができるでしょうか。
休業損害は、交通事故で負った怪我により仕事を休まざるを得なかった場合に、そのことによる収入の減収分の損害のことをいいます。休業損害は、「基礎収入(1日当たりの収入)」×「休業日数」で損害額を算定します。
パートを休んで得られなかった収入はもちろん休業損害の対象となります。また、「主婦(主夫)の家事労働」についても経済的に評価することができるので、交通事故により家事労働をできなくなった場合にも休業損害が発生します。この場合、家事従事者の「基礎収入」には、「(全年齢)女子の平均賃金」を用いることになります。
ただし、兼業主婦の方のように、「パートなど仕事で得た収入」と「家事労働」の両方が認められる場合であっても、いずれか高い方のみを休業損害として請求することができます。具体的には、「仕事(パート)で得た現実の収入」と「(全年齢)女子の平均賃金」とを比較し、高い方のみを「基礎収入」とすることになります。このような取り扱いがなされるのは、兼業主婦の方は、専業主婦の方と比較して、仕事に時間を使っていて、その分だけ家事労働の時間が減っていると考えられているからです(仕事と家事労働で二重に休業損害を認めると、専業主婦の方との間で公平を損なうと考えられています) 。 -
私はいわゆる「専業主夫」なのですが、交通事故に遭い、治療のため、しばらく家事をすることができませんでした。「専業主夫」は休業損害の賠償を求めることができるでしょうか。
専業主婦や専業主夫など、性別問わず「家事従事者」に該当する方は、事故により家事労働ができなくなった場合、休業損害を請求することができます。休業損害は、交通事故で負った怪我により仕事を休まざるを得なかった場合に、そのことによる収入の減収分の損害のことをいいます。休業損害は、「基礎収入(1日当たりの収入)」×「休業日数」で損害額を算定します。そして、家事従事者の「基礎収入」には、「(全年齢の)女子の平均賃金」を用います。この基準は、家事労働ができなくなった方が専業主夫の方(男性)である場合も同様です。
ただし、保険会社が、その男性が家族のために継続的に家事労働を行っているかをしっかり確認するために、「(女性の家事従事者の場合には提出不要である)資料」の提出を求めることがあります 。具体的には、家族全員の収入が把握できる資料(源泉徴収票や確定申告書など)の提出 が必要となることがあります。 -
私は、一人暮らしをしています。交通事故にあう前は、家事をしっかりと行っていました。しかし、事故でケガをしたせいで、治療期間中は、ほとんど家事をすることができませんでした。この場合、休業損害を請求することはできるでしょうか?
家事従事者が、交通事故により家事をすることができなくなった場合、休業損害を請求することができます。しかし、ここでいう「家事」は「他人のために行うもの」を前提としており、「自己のための家事」は含まれません。そのため、一人暮らしの方が交通事故に遭い、「自己のためにしていた家事」を行うことができなくなったとしても、これによって生じた損害を休業損害として請求することは困難であるといえます。
ただし、一人暮らしであっても、親族の家事・お世話をしに行っていたなどの事情がある場合には、他人のために行う家事に当たる可能性があります。 -
私は、一人暮らしですが、近所に住む高齢の母の家事や介護を手伝っていました。この場合、家事従事者として休業損害を請求することができるでしょうか?
家事従事者が、交通事故により家事をすることができなくなった場合、休業損害を請求することができます。しかし、ここでいう「家事」は「他人のために行うもの」を前提としており、「自己のための家事」は含まれません。そのため、一人暮らしの方が交通事故に遭い、「自己のためにしていた家事」を行うことができなくなったとしても、これによって生じた損害を休業損害として請求することは困難であるといえます。
ただし、一人暮らしであっても、親族の家事・お世話をしに行っていたなどの事情がある場合には、他人のために行う家事に当たる可能性があります。本件のように、一人暮らしとはいえ、近所にお住いのお母さんの家事・介護を手伝っていた事情があり、交通事故に遭ったことで家事・介護ができなくなった場合には、例外的に休業損害の請求が認められることがありうると考えられます。
なお、実際の裁判例でも、被害者の方が親族の家事を担っていた事情がある場合に、休業損害を認めたものがあります。以下では、いくつかの裁判例 をご紹介いたします。
①【東京高裁平成28年12月27日】:事故当時82歳で、長男夫婦と同居していた被害者の方につき、女性70歳以上平均賃金の80%の金額を基礎収入とする休業損害が認められた。
②【東京地裁平成18年6月15日】:事故当時91歳で、洋品店を経営する次女と同居していた被害者の方につき、洋品店の店番を時折していたが給与収入を得ていなかったこと、家事は次女と分担していたことから、女性65歳以上平均賃金の60%の金額を基礎収入とする休業損害が認められた。 -
私は、両親と弟の四人家族で暮らしています。家事は、私と母で半々くらいで分担して行っていました。交通事故によるケガの影響で、治療期間中に家事をすることができませんでした。この場合、家事従事者としての休業損害を請求することはできるでしょうか?
休業損害は、「基礎収入(日額)」×「休業日数」で算定します。そして、家事従事者が交通事故に遭ったことで家事を行えなくなった場合についても、「(全年齢の)女性の平均賃金」を基礎収入として、休業損害を請求することができます。ただし、家事を家族内で分担していた場合には、それぞれの家事従事者の基礎収入は、家事従事の貢献度に応じて、上記「(全年齢の)女性の平均賃金」から減額された金額で算定することになります。
本件のように、あなたとあなたのお母さんが半々で家事を分担していた場合、2人とも休業損害を請求することができますが、それぞれの基礎収入は、「一人で家事をしていた場合の休業損害の半分」として、休業損害が認定される可能性が高いです。 -
自賠責保険では、兼業主婦の休業損害は、どのような基準で支払われますか?
兼業主婦の休業損害の算定に当たっては、「仕事から得た現実の収入額」と「(全年齢の)女性の平均賃金」とを比較し、いずれか高い方が「基礎収入」となります。そして、「基礎収入(1日当たりの収入)」×「休業日数」により、休業損害額が算出されます。
もっとも、自賠責保険では、以下のような「自賠責基準」が妥当し、その限度でのみ休業損害の賠償がされるため注意が必要です。
(1)①自賠責基準における休業損害(1日当たり)
自賠責基準では、休業一日当たり「6100円」が基準とされています。裁判所基準のように「1日当たりの休業損害額(≒実損額)」で算出されないため、注意が必要です。
(2)②自賠責保険において、後遺障害を除いた傷害分の保険金の支払限度額
自賠責保険には、賠償額の合計金額にも限度額があります。「後遺障害を除いた傷害分の保険金の支払限度額」は、「120万円」と設定されています。ここでいう限度額は、休業損害だけでなく、治療費や慰謝料なども含んだ金額を指します。そのため、治療費等の金額によっては、自賠責保険のみでは休業損害を補填しきれないおそれがあるといえます。 -
私は、兼業主婦です。保険会社から、「週に30時間以上、会社員として働いているので、主婦休損は認めません。」と言われました。主婦休損の請求を諦めないといけないのでしょうか。
兼業主婦の方であっても、主婦休損(家事労働についての休業損害のこと)を請求できる場合があります。ただし、兼業主婦の休業損害の算定にあたっては、「仕事から得た現実の収入」と「(全年齢の)女性の平均賃金」を比較して、いずれか高い方が「基礎収入」となります。そして、「基礎収入」×「休業日数」で休業損害額を算定することができます。
本件では、あなたは、会社員として週30時間働かれているとのことです。
(1)その収入が「(全年齢の)女性の平均賃金」を上回る場合には、その1日当たりの収入が「基礎収入」となります。一方で、(2)下回る場合には、主婦休損、すなわち、「(全年齢の)女性の平均賃金」が「基礎収入」となります。
ただし、週30時間以上仕事をされている兼業主婦の方については、以下の点に注意する必要があります。
①自賠責基準によると、自賠責保険は、週30時間以上働いている方には主婦休損が支払われないこと。
②任意保険会社も、自賠責基準にならって、週30時間以上働いている方の主婦休損を否認(拒否)する場合があること。
③①②はあくまで「自賠責基準」に過ぎないこと。 →裁判所で調停や訴訟を提起した場合、週30時間以上働いている兼業主婦の方であっても、家事に支障が生じていたことを立証することで、主婦休損が認められる場合がある。 -
私は、会社の取締役をしています。休業損害を請求することはできるでしょうか?
会社の取締役など役員の方は、基本的に休業損害を請求することはできません。「休業損害」は、会社役員は、委任契約に基づいて役員報酬を受け取っており、休業しても基本的には報酬が減らないからです。
もっとも、役員報酬が減少した場合に、例外的に休業損害を請求できることがあります。役員報酬には、「労務対価部分」と「利益配当の部分」がありますが、このうち前者の「労務対価部分」は、従業員の給与と同じような性質を有すると考えられるからです。役員報酬のうち「労務対価部分」がどれほど含まれるかは、会社の規模・収益状況、当該役員の地位・職務内容・役員報酬額、他の役員との比較など、個別具体的な要素を総合的に考慮して判断します。
たとえば、会社役員とはいえ、自ら技術者として働いたり、肉体労働を行っていたりして、その労務を代替しうる従業員がいない場合には、役員報酬の大部分に「労務対価性」が認められ、休業損害が認められる可能性があります。 -
私は、会社役員をしています。交通事故による重傷を負い、約3か月間、入院をしていました。入院期間中は、当然、会社に出社することができず、役員としての仕事は全くすることはできませんでした。しかし、私は、会社役員なので、役員報酬は入院期間中も満額支給されました。この場合、私が休業損害を請求できないのはわかりますが、会社は何か請求することはできないのでしょうか?
会社役員が交通事故に遭った場合に、会社が被る損害として考えられるのは、①役員が就労しなかった場合でも、役員報酬を支払ったとき、②役員の休業によって会社の事情活動に影響が出て、会社の営業利益が減少したときなどが挙げられます。なお、このように、交通事故被害者以外の者に発生した損害のことを「間接損害」といいます。
①の損害は、会社が役員に生じた休業損害を肩代わりして賠償することによって発生するため、基本的に加害者側に対してその賠償を求めることができます。しかし、会社役員の休業損害は、役員報酬のうち「労務対価部分」について認められると考えられています。詳しくは、※【90)】をご参照ください。そのため、たとえ会社が役員報酬全額を肩代わりしたとしても、加害者側に請求できるのは、役員報酬のうち「労務対価部分」に限られるため、注意が必要です。
②のような損害は、従来賠償が認められない傾向にありましたが、近年認められる裁判例が出てきています。会社が②の損害賠償を求めることができるか否かのポイント(分かれ目)は、「会社と役員(被害者)との間に経済的一体性が認められるかどうか」ということです。具体的には、会社の規模が小規模で、会社の営業活動と役員個人の営業行為が実質的に同一と評価できるような場合は、会社の営業利益の減少分の賠償が認められる可能性があります。 -
休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。
-
私は会社で働いているのですが正社員ではありません。交通事故に遭って、しばらく会社を休まざるを得なかったのですが、正社員でなくても休業損害の賠償を求めることはできるのでしょうか。
正社員でない方も、休業損害を請求することができます。
請求の仕方は、正社員の方と同様に、①勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらい、これと併せて②「源泉徴収票」を加害者側の保険会社に提出しましょう。①は事故前の欠勤日を確認するため、②は事故前の基礎収入を確認するための書類です。詳しくは、【69】をご参照ください。 -
交通事故でけがをさせられたので仕事を休まなければならなかったのですが、有給休暇を使ったので結果的に収入に影響はありませんでした。このような場合でも、休業損害を請求できるでしょうか。
交通事故の治療のために有給休暇を使用した場合には、これによる減収は生じていないため、休業損害が認められないようにも思えます。
しかし、本来であれば他の目的に利用できたはずの有給休暇を、交通事故の治療のために使用しなければならなかったのですから、その結果、本来有給休暇が使用できたのに欠勤となる場合も十分あり得るし、失った余暇等のための時間は財産的価値を有するものといえます。
そのため、実務上は、治療のために有給休暇を利用した場合であっても、休業損害が請求できるものと解されています。 -
事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
-
公務員のため、休業しても給料は減りません。それでも休業損害はもらえるのでしょうか。
減収が無い場合はもらえません。ただし、有給休暇を使用していたり、付加給が支給されないなどの事情がある場合は、もらえる可能性もあります。
-
私は自営業者です。事故で休業しているのですが、確定申告をしていないため、保険会社から休業損害は出ないと言われてしまいました。休業損害は諦めなければならないのですか。
休業損害とは、事故前の収入と、事故後の収入を比べて、事故後に減収がある場合、それを埋め合わせるための賠償です。事故前後の比較は、原則として確定申告書などの公的資料で行いますので、確定申告をなさっていないというのは、不利なスタートだと言わざるを得ません。 ただし、預金口座の出入金記録などで事故前後の収入状況の比較ができる場合、休業損害の請求ができますので、あきらめずにご相談ください。
-
主婦が交通事故に遭い、治療期間中は家事ができなかった場合、休業損害を請求することができるでしょうか。
主婦のような家事従事者については、主婦として稼働できなかったとしても減収が生じていないため、休業損害は請求できないようにも思えます。 しかし、実務上は、家事従事者が家事労働に従事できなかった場合にも、休業損害を請求することが認められています。その金額は、女性の全年齢平均賃金を基礎として計算するのが原則ですが、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、これよりも低い金額になる場合もあります。
-
交通事故に遭って、治療のためしばらく働ける状況にありませんでした。事故当時、私は無職だったのですが、就職活動中でした。このような事情から、加害者に対して休業損害の賠償を求めることはできませんか。
事故当時に収入がない場合、原則として休業損害の賠償を求めることはできません。休業損害は、被害者が交通事故により休業せざるを得なかった場合に、「事故当時の収入」と「事故後の収入」とを比較し、「その減少分(差額)」を損害とするものであるからです。
しかし、交通事故に遭った当時、無職の方であっても、労働能力や労働意欲があり、実際に仕事に就く可能性(就労の蓋然性)がある場合には、休業損害が認められる可能性があります。その際には、被害者の年齢や身につけている技能・資格、就労意欲、治療期間の長さなどがポイントとなります。
たとえば、①学生や若年の方は、労働能力や就労の蓋然性が認められやすい傾向にあります。また、②治療期間が長い場合、その間に仕事に就いていた蓋然性(可能性)が高まるため、休業損害が認められやすくなります。さらに、③就職活動の内容が具体的である場合(ex.面接まで進んでいる)、休業損害が肯定されやすくなります。
無職の方の休業損害を認める場合、「基礎収入」をどのように算出すべきかが問題となります。事故当時収入を得られていなかったことから、「基礎収入」は基本的に「労働者の平均賃金(賃金センサス)を下回る金額」をとすることが適切であると考えられています。ただし、既に内定を得ている場合には、そこでの給与額を「基礎収入」とすることが可能と考えられています。また、内定を得ていない場合でも、被害者の方の失業前の収入の水準や失業の経緯、年齢、身につけた技能・資格などによっては、「賃金センサスと同等又はそれ以上の金額」を基礎収入とすることが認められることがあります。 -
大学生の息子が交通事故にあいました。休業損害を請求することはできるでしょうか?
大学生などの学生や中学生・高校生などの生徒であっても、交通事故に遭った場合、事故当時に収入を得ていれば、休業損害の賠償を求めることができます。休業損害は、被害者が交通事故により休業せざるを得なかった場合に、「本来得られたはずの収入の減収分」を損害とするものであるからです。
また、大学生や高校生・中学生が、交通事故に遭って治療を余儀なくされるなどして就職が遅れた場合にも、休業損害の賠償を求めることができます。なお、交通事故に遭って進学・進級が遅れた結果、就職も遅れた場合も賠償を求めることができます(ex.交通事故に遭って大学受験ができず、事故翌年に大学に入学した場合→事故がなければ事故の年に入学できていたとして、1年分の休業損害が認められた。)。 -
交通事故に遭って、治療のためしばらく働ける状況にありません。そのため、仕事を休まざるを得ず、収入を得られていません。なんとか保険会社に生活費を支払ってもらうことは可能でしょうか。
「内払い」という形で、休業損害や慰謝料の一部を先に支払ってもらえる場合があります。弁護士から保険会社に内払いをするよう通知をすることができます。
もっとも、保険会社には内払いをしなければならない義務はなく、いつまで支払いが続くかは個別の状況によります。お身体に無理のない範囲でお仕事に復帰されることをおすすめします。
-
休業損害は、いつまで請求することができますか?
休業損害は、症状固定までの間で、休業を余儀なくされ得られなかった収入(減少分)を請求することができます。
休業損害とは、被害者が交通事故に遭って、治療などのために休業せざるを得なかった場合に、「(症状固定時までに)本来得られたはずの収入の減収分」を損害とするものです。休業損害の算定は、基本的に、「(1日当たりの)基礎収入」×「休業日数」で行います。「休業日数」は、休業している期間全てが認められるとは限りません。基本的には、「休業せざるを得なくなった日から症状固定日まで」の日数が「休業日数」となります。「症状固定」とは、治療してもこれ以上良くならない状態のことをいいます。この状態に至った場合、これ以上休業をして損害が発生したとしても、休業損害を請求することはできません。
なお、交通事故がなければ得られたであろう収入のうち、症状固定後に発生するはずであった収入の減収分については、「後遺障害逸失利益」として、請求することができます。ただし、「後遺障害逸失利益」は、後遺障害認定を得ることが前提となります。詳しくは、※【96】をご参照ください。