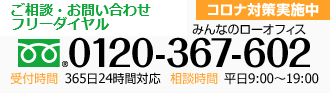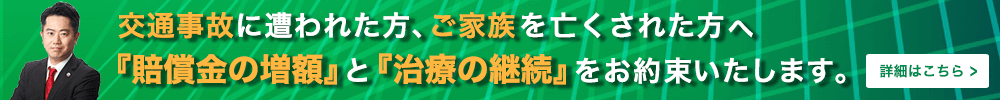【胸椎骨折・後遺障害】後遺障害12級から併合7級へ!
音声でも解説をご用意しています。
70代女性がセカンドオピニオンで獲得した賠償金約1,180万円の増額事例
交通事故で胸椎骨折や脛骨プラトー骨折を負い、後遺障害等級認定に不満を持つ70代女性の解決事例をご紹介します。以下では、当初12級と認定された後遺障害等級を、異議申立てにより併合7級に引き上げ、最終的に約1,180万円の賠償金(既払い金含む)を獲得した事例を紹介いたします。
セカンドオピニオンの重要性や、適切な医療調査と弁護士の戦略がどのように高額な賠償金に繋がるのかを、具体的なケースを通じてご理解いただけます。交通事故の後遺障害でお悩みの方、現在の等級認定に疑問をお持ちの方は、ぜひご一読ください。専門家への相談が解決への第一歩となることでしょう。
相談者のプロフィール:自立した生活から一転、日常生活に大きな支障が
今回の解決事例の相談者であるSさんは、70代の女性です。事故前は無職でしたが、以前は不動産賃貸業を営んでおり、3階建てアパート3棟の管理や清掃作業を自身で行うなど、非常に活動的な生活を送っていました。また、家事も自立してこなし、週に1回ヘルパーに清掃を依頼する程度でした。徒歩での移動も問題なくできていたといいます。家族は、遠方に住むお子さんがいらっしゃいます。
しかし、今回の交通事故により、Sさんの生活は一変しました。Sさんは胸椎骨折(背骨4~5本を骨折し、ボルトが10~15本入る手術を要する)と脛骨プラトー骨折(右足の膝裏の骨折、脛の骨が割れる)という重傷を負い、日常生活に大きな支障が生じてしまいました。特に、事故前は問題なくできていた階段の上り下りや、畳に座ってから立ち上がること、正座といった動作が非常に困難になりました。重い荷物を持つことや、和式トイレの使用も難しく、足の裏のしびれ、腰とお尻の痛み、そして右腕・右手の痛みも残存しました。
事故の概要:信号のない交差点での右折車との衝突事故
事故が発生した場所は、信号も横断歩道もない市街地の小さな交差点です。Sさんは歩行者として交差点を横断していました。その際、右折しようと停車していた自動車がいました。Sさんが渡り終える寸前、右折車が携帯電話を見たのか、突然発進し、Sさんに衝突しました。この衝突により、Sさんは多発性の胸椎骨折(特に第12胸椎の破裂骨折)と右脛骨プラトー骨折という非常に重篤な傷害を負いました。Sさんは事故後すぐに病院に救急搬送され、約4か月の入院治療(113日間)を受けました。
相談時の悩み・課題:後遺障害12級認定に納得できない、専門知識の不足
1. 別の弁護士に依頼するも等級アップの可能性を相談したかったのはなぜ?
被害者Sさんは、事故後、すでに別の法律事務所に交通事故の解決を依頼していました。その法律事務所からは、Sさんの後遺障害等級として12級が認定されたと伝えられました。しかし、Sさんは主治医から「うちの病院で1、2を争う酷い事故だった」と聞いており、後遺症が残るとも言われていたため、認定された12級という等級に疑問を抱いていました。
前の弁護士からは、後遺障害について詳しい説明がなく、適切な手続がされていないのではないかという不安を抱いていました。特に、後遺障害の異議申立てに関する具体的な説明が不足しており、このまま任せていて良いのかという不信感がありました。
Sさんは、現在の生活の困難さを考えると、もっと上位の等級が認められるべきだと考えていました。そこでSさんは、より専門的な知識と経験を持つ弁護士に「もっと詳しく話を聞きたい」「上位の等級が認定される可能性はないか」という思いから、当事務所にセカンドオピニオンを求めて相談に来られました。
2. 事故前の生活とのギャップと深刻な身体的苦痛
事故前は自立した生活を送っていたSさんですが、胸椎骨折や脛骨プラトー骨折という重傷により、その生活は一変してしまいました。特に、3階建てのアパートの自宅の階段を上り下りすることや、正座や畳に座る動作、重いものを持つことが困難になり、日常生活に大きな支障が出ていました。痛みやしびれにより、動くのが非常につらいという状態でした。
初回の後遺障害診断書では、右脛骨プラトー骨折後の疼痛により、歩行速度が遅く、重い荷物が持てない、正座や和式トイレが困難であることなどが記載されていましたが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定に留まりました。胸腰椎部の運動障害については、可動域が参考可動域の1/2以下に制限されていないとして、後遺障害には該当しないと判断されていました。さらに、既存障害として、事故以前から有していた第3腰椎の圧迫骨折が「せき柱に変形を残すもの」として11級と評価されていました。Sさんはこの結果に納得できず、等級変更を強く望んでいました。
弁護士の対応・戦略:セカンドオピニオンから始まった異議申立てへの道
1. 徹底した医療記録の分析と再評価の必要性
当事務所がSさんの代理人として受任後、まず行ったのは、詳細かつ徹底的な医療調査でした。Sさんの全ての医療記録(カルテ、画像検査結果、後遺障害診断書など)を医療機関から取り寄せ、これらを綿密に分析しました。これは、初回認定時の資料だけでは、後遺障害の全体像やその重篤度が適切に評価されていない可能性があったためです。
医療調査会社による分析も実施した結果、当初は「圧迫骨折の変形障害での等級変更は難しい」との見解もありました。特に、脊椎の画像データが限定的であったため、「脊髄判定用」に該当する神経症状の有無や、脛骨プラトー骨折後の症状と既存障害の複合的な影響が評価を困難にしていました。
しかし、担当弁護士は諦めず、症状固定時に主治医(大分赤十字病院の安部大輔医師)が「症状緩解の見通しはない」と所見していた点に着目しました。症状固定後も症状が不変であったことから、安部医師に現在の症状の再評価と、新たな医証(後遺障害診断書)の作成を依頼しました。
2. 後遺障害等級8級認定の妥当性を主張した異議申立て
再評価の結果、新たな後遺障害診断書が発行され、Sさんの胸腰椎の可動域制限が、原則通りの認定基準を適用しても8級2号の評価となることが判明しました。
当事務所は、この新たな医証に基づき、初回認定時の判断が形式的かつ硬直的であり、実際の障害実態を反映していないことを強く主張し、異議申立てを行いました。具体的には、初回認定時の後遺障害診断書に記載された胸腰椎の主要運動の可動域合計が45度であり、参考可動域角度の1/2である37.5度をわずか2.5度上回る(42.5度以下に制限されていない)という形式的な理由で、脊柱の運動障害が評価されなかった点を指摘しました。
しかし、実際には、後屈、右屈、左屈の運動方向でほとんど可動しない制限が残っており、主要運動と参考運動(左右屈)を合計した可動域値は、8級2号の基準(92.5度)を大きく下回る65度であったことを強調しました。これにより、「労災補償 障害認定必携」の規定にある「わずかに上回る場合」の例外規定を適用し、実態に即した評価として8級2号の認定を求めました。この綿密な医療調査と法的な根拠に基づいた異議申立ての結果、Sさんの後遺障害等級は大幅に改善されることになります。
解決結果:後遺障害等級が併合7級にアップ!賠償金も大幅増額
徹底した医療調査と粘り強い異議申立ての結果、最終的に、被害者Sさんの後遺障害等級は、当初の12級から併合7級に認定が変更されました。これは、交通事故による新たな脊柱の障害(胸椎骨折による運動障害)が8級相当と評価され、事故によって悪化した既存の膝の障害(脛骨プラトー骨折後の神経症状)12級と併合された結果です。
なお、既存障害として、事故以前から有していた第3腰椎の圧迫骨折が11級と判断されたため、その分の賠償金は控除されました。この等級変更により、賠償金も大幅に増額され、最終的な既払い金を除く支払額は1,180万円となりました。これは、セカンドオピニオンを求め、適切な弁護士に対応を依頼した結果、得られた大きな成果と言えるでしょう。
| 損害項目 | 受任前提示額 | 受任後獲得額 | 増額額 |
|---|---|---|---|
| 休業損害 | 提示なし | 約240万円 | 約240万円 |
| 傷害慰謝料 | 提示なし | 約400万円 | 約400万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 290万円 | 約600万円 | 約310万円 |
| 既払い除く支払額 | 提示なし | 約1,180万円 | 約1,180万円 |
担当弁護士のコメント:なぜ異議申立てが成功し、等級が変更されたのか?
本件の解決ポイントは、被害者Sさんが自賠責保険における後遺障害認定結果に納得せず、当事務所にセカンドオピニオンを求めてくださった点に尽きます。交通事故の経験が豊富な弁護士でなければ、自賠責保険の後遺障害手続を適切に進め、その認定結果を正確に評価することは困難です。Sさんの以前の弁護士は、後遺障害手続を加害者側の保険会社に任せる「事前認定」という方法を取っており、この手続では被害者にとって不利な結果となることが多いのが実情です。
今回のケースも、当初は医療調査会社から「画像から変形障害での等級変更は難しい」という見解もあり、非常に困難なケースでしたが、主治医に再評価を依頼し、医証を取り付けた結果、異議申立てが認められました。異議申立ての主たる主張は胸腰椎の運動障害でしたが、前回提出された後遺障害診断書の数値が有効とされ、可動域悪化の客観的医学的所見がないとして一度は否定されていました。それでも、結果として等級変更が認められたことは、大変良い成果です。
Sさんは、事故前は自立した生活を送っていましたが、事故によりそれが困難になり、日常生活に大きな支障をきたしていました。今回の等級変更が実現し、「良い方向に進んで良かった」と依頼者様から喜びの声をいただけたことは、私たちにとって何よりの励みとなります。
まとめ:胸椎骨折や後遺障害でお悩みなら、専門家へのセカンドオピニオンが重要
交通事故によって胸椎骨折や脛骨プラトー骨折のような重傷を負い、後遺障害が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級認定を受けることは、その後の生活を大きく左右します。今回の事例のように、一度認定された等級に納得できない場合でも、適切な医療調査と専門家による異議申立てを行うことで、等級が変更され、賠償金が大幅に増額する可能性があります。
特に、他の弁護士に依頼しているものの、後遺障害の等級認定に疑問がある、または専門的な知識が不足していると感じる場合は、当事務所のような交通事故に強い弁護士にセカンドオピニオンを求めることが極めて重要です。専門的な視点から医療記録を精査し、必要な医証を収集することで、等級アップの道が開けることがあります。
後遺障害に関するお悩みや不安は、一人で抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を共に探し、より良い未来を築くためのお手伝いをさせていただきます。
- 橈骨骨折・尺骨骨折で後遺障害12級!
- 足関節可動域制限で後遺障害10級11号を獲得!
- 膝内側靭帯断裂の後遺障害で14級相当!
- 【腰椎・胸椎骨折】後遺障害11級を獲得
- 時効の壁を乗り越え、約424万円を獲得!
- 高齢者の死亡事故の訴訟で慰謝料 約4,000万円の認定
- 顔の傷で後遺障害12級を獲得!
- 【自賠責なし・車検切れで労災14級】訴訟で約340万円を獲得し早期解決した事例(20代男性)
- 手足の傷痕で後遺障害14級5号認定!
- 【外貌醜状(顔の傷)で後遺障害9級】医師面談と自賠責の面接調査への同行で受領総額約1,416万円を確保した解決事例(40代男性)
- 【外貌醜状(顔の傷)で後遺障害12級】10代男性が逸失利益ゼロ提示から覆して約710万円を獲得した解決事例
- 【解決事例/080】単身者であったが家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース(後遺障害 併合7級)
- 家族間の事故の保険は諦めない!胸椎骨折で後遺障害6級5号認定、賠償金0円提示から約820万円獲得の解決事例
- 【解決事例/078】高次脳機能障害が見落とされていることに気付き、後遺障害7級4号が認定された事案
- 【解決事例/077】高次脳機能障害で後遺障害1級が認定され、約3億7000万円の賠償が認められた事例
- 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。
- 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例
- 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例
- 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例
- 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例