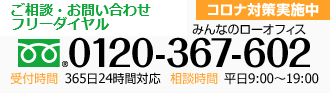高次脳機能障害とは?定義や症状から診断、治療方法、リハビリ期間まで解説
先日、当事務所の弁護士が、専門家向けの高次脳機能障害の研修に参加しました。
この研修では、交通事故などが原因で脳にダメージを受けた方に起こる「高次脳機能障害」について、その認定の仕組みや、実際に裁判などでどのように判断されているかについて、最新の事例などを踏まえ、深く学ぶ貴重な機会となりました。
この研修で得た知識を活かし、皆さまがより適切にサポートを受けられるよう、最善を尽くしてまいります。
今回の研修では、特に以下の3つのテーマについて深く掘り下げて学びました。
- ①自賠責保険の認定基準を踏まえた実務上の留意点
- ②自賠責保険・共済紛争処理機構の判断傾向
- ③裁判所の判断傾向
1.自賠責保険の認定基準を踏まえた実務上の留意点
(1)事故による脳のダメージが原因の症状かどうかの審査
- ア 入口の審査 高次脳機能障害は、交通事故などで脳に器質的な損傷(目に見えるダメージ)を受け、一時的に意識がはっきりしない状態が続いた後、記憶力の低下や性格の変化といった症状が現れる障害です。これらの症状が本当に脳のダメージによるものだと、医学的に認められるこが、障害として認定されるための第一歩です。
- イ 入口の審査におけるポイント
- (ア)脳の画像検査(CT・MRIなど)
事故の直後に、脳の中に出血や打撲がないか、また、時間が経ってから脳が萎縮したり脳室が広がったりしていないかを確認します。特に、ごく小さな脳の損傷を見つけるためには、CT検査よりも、MRI検査(T2強調画像、T2*、DWI、FLAIRなど)が重要となります。
なお、DTI、fMRI、MRS、SPECT、PETといった特殊な検査だけでは、脳の損傷を確定的に示すことはできず、これらの検査は、あくまで参考情報として扱われます。 - (イ)意識障害の有無と程度 事故の直後、どれくらいの時間(例えば約6時間以上)、どのくらいの程度意識がはっきりしなかったかが、脳のダメージにより高次脳機能障害が起きた可能性の高さを判断する重要な目安となります。これは、医師の記録や救急隊、警察の記録など、様々な情報から判断されます。
- (ウ)総合的な判断
自賠責保険では、これらの画像所見や意識障害の有無・程度を中心に、事故による脳へのダメージで高次脳機能障害となったかどうかを判断しています。ただ、画像所見と意識障害のみで判断するのではなく、神経心理学検査の結果やその他の様々な事情を総合的に見て、高次脳機能障害として認められるかどうかを判断します。
総合的な判断とはいえ、自賠責保険では、画像所見が弱いケースでは、いかに症状が重くても高次脳機能障害を否定する傾向にあり、画像所見が重視されています。
- (ア)脳の画像検査(CT・MRIなど)
事故の直後に、脳の中に出血や打撲がないか、また、時間が経ってから脳が萎縮したり脳室が広がったりしていないかを確認します。特に、ごく小さな脳の損傷を見つけるためには、CT検査よりも、MRI検査(T2強調画像、T2*、DWI、FLAIRなど)が重要となります。
(2)障害の重さの評価(どの等級の高次脳機能障害かの認定)
- ア 基本的な考え方
高次脳機能障害の重さは、主に、以下の4つの能力がどれくらい失われたかという観点から判断されます。
- ①意思疎通能力: 物忘れ、記憶力、理解力、言葉の能力など。
- ②問題解決能力: 物事を理解し、判断する能力など。
- ③作業を持続する集中力。
- ④社会で適切に行動する能力: 協調性など。
- イ 神経心理検査の評価 神経心理学検査(WAIS-III・IVなど)も参考にされますが、その結果だけで障害の重さが決まるわけではありません。例えば、検査では知能が高くても、実際の社会生活で問題行動がある場合は、障害が重いと判断されることがあります。
- ウ 脳損傷や意識障害の程度との関係 一般的には、脳の損傷が重いほど、または意識がはっきりしない期間が長いほど、障害も重たくなるとされています。ただ、脳損傷の程度が軽い場合でも、重たい高次脳機能障害となることもあり、これらの相関関係は絶対的なものではありません。
(3)障害の重たさの評価の大まかな目安
高次脳機能障害は、症状の重たさに応じて、1級から9級までの評価があります。自賠責保険における高次脳機能障害の症状の重たさの判断の大まかな目安は、以下のとおりです。
(4)子どもと高齢者の特殊性
- ア 子ども 子どもの場合、脳の成長や精神機能の発達が影響するため、すぐに障害の重さを判断するのが難しいことがあります。特に、軽度の障害では、学校生活に適応できる時期まで様子を見るなど、時間をかけた観察が大切です。早急に判断すると、本来よりも軽く評価されてしまうリスクがあります。
- イ 高齢者 高齢者の場合、年をとることによる物忘れや認知機能の低下が事故の影響と重なることがあります。事故後に症状が悪化しても、それが事故のせいなのか、加齢によるものなのかを医学的に見極めることが重要です。交通事故の外傷により、通常の加齢による変化を超えて悪化していると明確に証明できない限り、等級が上がることはありません。
2.紛争処理機構の判断傾向
(1)紛争処理機構とは
自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険・共済の判断について審査をしてくれる第三者機関です。
紛争処理機構での高次脳機能障害の審査の際も、審査基準は自賠責保険の審査の場合と同じ審査基準で審査されます。ただし、意識障害の有無や程度、画像所見の経過などをより詳しく審査されることで、自賠責保険が当初「高次脳機能障害ではない」と判断したケースでも、紛争処理機構が「高次脳機能障害である」と認めるケースもあります。
(2)ケース別の判断傾向
- ア 画像所見がないケース 画像に異常がなく、事故後の意識障害がない又はとても軽い場合は、高次脳期障害が認められないことが多いです。
- イ 脳挫傷の画像所見のみがあるケース
画像上、脳室拡大や脳萎縮がなくても、脳挫傷があり、かつ、軽度や中程度の事故後の意識障害があれば、高次脳機能障害が認められることがあります。
このようなケースは、自賠責保険では高次脳機能障害が否定されることが多いので、紛争処理機構で自賠責の結果が変わりやすいケースといえます。 - ウ 明らかな画像所見があるケース
画像上、脳萎縮や脳室拡大、びまん性軸索損傷がある場合には、事故後の意識障害が軽い場合でも、高次脳機能障害が認められることが多いです。
ただし、事故後の意識障害が軽い場合は、等級は低くなりやすい傾向があります。 - エ 脳外傷がないのに高次脳機能障害を認めた特殊なケース その他、特殊なケースとして、脳外傷がないものの、事故前からあった認知症が、事故により長く寝たきりになることで認知症が急激に悪化したとして、事故による高次脳機能障害を認定してケースがあります。
長く寝たきりになることで、認知症が進行することがあります(「廃用症候群」といいます。)。それを前提に、事故後の認知症の悪化が、通常の加齢による変化を超えていて、事故により認知症が悪化したことが明らかかどうかが審査されています。
3.裁判所の判断傾向
(1)自賠責や紛争処理機構の認定基準や判断との関係
裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の認定基準や判断結果に拘束されません。そして、裁判所で確定した判断が最終的な判断となります。
(2)脳外傷による高次脳機能障害かどうかの認定
- ア 裁判所の判断傾向 裁判所は、自賠責保険の認定基準には拘束されません。しかし、裁判所も、自賠責保険の判断基準を参考に高次脳機能障害の有無を判断することが多いとされています。したがって、裁判所と自賠責保険とで、認定基準に大きな差はありません。
- イ 自賠責否定・裁判所肯定のケース
自賠責保険は、画像所見を重視するので、画像所見が乏しい場合は、高次脳機能障害が認められないケースが多いです。
このようなケースで、厚生労働省が示す高次脳機能障害の診断基準を用いたり、事故状況から頭部への衝撃の大きさを認定したり、CTやMRI以外の画像所見から高次脳機能障害を認定した裁判例もあります。ただし、このような裁判例の数は多くありません。 - ウ 自賠責肯定・裁判所否定のケース
自賠責保険が高次脳機能障害を肯定したのに、裁判所が否定したケースは、数多くあります。
裁判所が否定するケースは、自賠責保険の等級認定後に時間が経ち症状が改善したことや、裁判になってから初めて提出された証拠(カルテなどの医療記録、本人の生活状況や就労状況についての資料など)によって、自賠責の認定が覆されることが多いです。
(3)障害の重さの認定
- ア 裁判所の判断傾向
障害の重さの認定は、労災保険の基準による裁判例が多いです。この基準は、4つの能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力)の喪失程度を6段階で評価するという基準で、自賠責保険の基準に比べると、より具体的な基準です。
自賠責保険が示した基準(本記事の1⑶に記載した基準)によって障害の程度を判断する裁判例もありますが、そのような裁判例は少ないです。 - イ 自賠責の等級よりも上げた裁判例 自賠責の等級よりも高い等級を認定した裁判例は少ないです。そのような裁判例は、自賠責の認定等級よりも労災保険の認定等級の方が高かった場合に、自賠責の認定と労災の認定のバランスを取って自賠責の等級を上げるような判断のことが多いです(例えば、自賠責が9級で労災が5級であった場合、裁判では7級とするような判断)。
- ウ 自賠責の等級よりも下げた裁判例
自賠責の等級よりも低い等級を認定した裁判例の方が圧倒的に多いというのが実情です。
これは、自賠責保険の等級認定後に時間が経ち症状が改善したことや、裁判になってから初めて提出された証拠(カルテなどの医療記録、本人の生活状況や就労状況についての資料など)によって、自賠責が認定する等級よりも実際の症状の程度は軽いと判断されることが多いためです。
4.高次脳機能障害と介護・生活支援の重要性
今回の研修では、高次脳機能障害の自賠責・紛争処理機構・裁判例の傾向だけでなく、認知症の方の在宅介護体制についても、在宅介護の現場に長く勤める講師から、多くのことを学ぶことができました。
高次脳機能障害の被害者の方は、事故後、日常生活に介護を必要とするようになる方も多いです。そのような場合、加害者からの賠償を得ることだけではなく、日々の生活を支える介護・生活支援の知識も、私たち弁護士にとってとても重要であることを再認識しました。
高次脳機能障害で、介護が必要な方の生活支援は、基本的に、介護保険制度のサービスと障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを利用することになります。
介護保険サービス
65歳以上の方や、特定の病気を持つ40~65歳未満の方が対象で、要介護度に応じて、訪問介護や通所介護、福祉用具のレンタルなど、さまざまなサービスが利用できます。
障がい福祉サービス
身体障害、知的障害、精神障害を持つ方が対象のサービスです。日常生活における課題のサポートを目的とした介護給付と、自立や就労を目的とした訓練等給付の2種類があります。介護給付・訓練等給付を合わせて18種類のサービスがあり、大きく「生活系、入所系、自立・就労系」に分けることができます。
介護保険サービスと障がい福祉サービスの住み分け
介護保険を利用できる方は、介護保険のサービスが優先されます。ただし、介護保険制度でカバーできないサービスや、支給限度額を超えてしまう場合には、介護保険の利用対象者でも、障がい福祉サービスも利用できます。
これらの制度を上手に活用することで、高次脳機能障害を持つ方やそのご家族が、長期的に安定した生活を送るための包括的なサポート体制を築くことができます。
今回の研修を通じて、高次脳機能障害に関する自賠責保険・紛争処理機構・裁判所の判断傾向について、最新の事例を踏まえたケース研究を行うことができました。自賠責保険・紛争処理機構・裁判所の判断傾向を踏まえたうえで、的確な判断と効果的な主張立証を行います。
当事務所は、今後も、このような専門研修に積極的に参加し、最新の知見や実務の傾向を常に把握してまいります。交通事故による後遺障害の中でも、特に難しいといわれる高次脳機能障害に関して、最適な法的支援を提供できるよう、より一層尽力していく所存です。