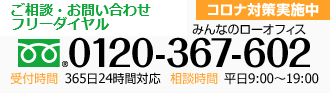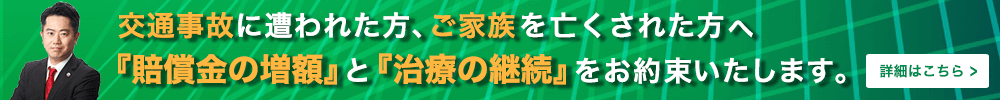【解決事例/049】医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース
| 依頼者属性 | 性別 | 男性 |
|---|---|---|
| 年代 | 40代 | |
| 職業 | 会社員 | |
| 事故態様と相談 | 事故場所 | 日田市 |
| 事故状況 | 国道をバイクで走行中、信号のない交差点で、左右確認をせずに右折をしてきた自動車と衝突した。 | |
| 相談のタイミング | 事故から6か月後 | |
| 相談のきっかけ | 保険会社から症状固定を提案されたので、今後のことについて相談したい。 | |
| 怪我と後遺障害 | 傷病名 | 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折 |
| 自覚症状 | 腹痛、下痢の間欠的持続 | |
| 後遺障害等級 | 併合第10級(11級10号、13級11号) | |
| 保険会社提示額 | 事前提示 | なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) |
| 獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
| 金額 | 約2130万円 | |
| 備考 | 治療費などを含めた賠償総額約2125万円 |
※治療費は労災にて支払われたため賠償の対象外
相談から解決までの流れ
道路をバイクで走行中に、対向車線から侵入してきた四輪車と衝突し、外傷性脾損傷、外傷性膵損傷、外傷性肝損傷、肋骨骨折、上腕尺骨骨折、手中指中手骨骨折の重傷を負ったケースです。事故から約6か月後に、保険会社から症状固定の打診がきたことから、今後の手続の流れについて知りたいとのことで相談にお越しくださり、受任に至りました。
受任後、まず、症状固定の時期についての検討を行いました。保険会社から診断書・レセプトなどの医療記録を取り寄せ、依頼者から現在の症状、治療の状況、症状の推移などをヒアリングし、それらを踏まえて、保険会社と症状固定の時期について交渉を行いました。交渉の結果、保険会社から症状固定の打診があった時点から、約6か月治療期間を延長することができました。
事故から約1年後に、主治医の見解も踏まえ、症状固定とすることになりました。ただ、症状固定をすることとなった後に、後遺障害診断書の作成について、問題となりました。依頼者が主治医から受けた説明によると、事故当初の重傷の状況からすれば、かなりの回復がみられ、内臓機能の数値も正常値ではないものの、大きな異常値でもないということで、後遺症は認定されないということで、後遺障害診断書の作成を断られたということでした。ただ、事故後に大きな回復はみせたといえ、完治には至らずに自覚症状もあり、大きな異常値ではないものの検査数値自体は正常値でなく、自賠責保険の後遺障害の基準は満たしていました。そこで、弁護士による主治医との医師面談を行い、自賠責保険の認定手続とその基準について説明を行い、後遺障害診断書を作成していただけることになりました。
その後、主治医による後遺障害診断書が作成されたので、その内容を確認したところ、依頼者が訴えている重要な自覚症状が診断書に記載されていませんでした。そこで、再度、医師面談を行い、後遺障害診断書の記載の不備について指摘したところ、不備の訂正に応じていただけました。
その後、自賠責保険に対して、被害者請求の方法で、後遺障害の認定の手続を行った結果、膵臓の障害について、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として11級10号の後遺障害が認定され、脾臓の障害について、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として、13級11号の後遺障害が認定され、2つの認定を合わせて併合10級の後遺障害が認定されました。
後遺障害の認定後は、相手方保険会社と賠償金の示談交渉を行いましたが、大きく揉めることはなく、裁判所基準をベースとした金額で、当方の主張する金額にほぼ近い金額でスムーズに示談に至りました。
担当弁護士の振返りポイント
今回のケースは、医師面談を複数回行い、不備のない後遺障害診断書を作成するなどして、被害者請求を行ったことで、適切な後遺障害が認定され、良い結果となりました。
医師の中には、後遺障害診断書の作成に積極的ではない医師もいます。特に、今回のように、事故によりかなりの重傷を負った患者が、その後、大きな回復を見せたものの、完治には至らずに、何らかの症状が残っているようなケースでは、医師が後遺障害診断書の作成を嫌がる傾向にあります。
ただ、医師のそのような気持ちもわからないではありません。医師としては、当初、生死の境をさまようような重傷であった患者が、その後、大きな回復を見せて日常生活を送れるほどに回復をしたのであれば、医師からみれば、「ほとんど治った」という側面が大きく、多少の症状が残っていたとしても、「後遺症が残った」という側面からは見ないのだと思います。ただ、完治はしておらず何らかの症状があるのであれば、自賠責保険の後遺障害の認定の対象になり、実際に後遺障害が認定されることも多くあります。この、医師が医学的に見た時の後遺症と、自賠責保険が認定する後遺障害との間のずれが、どうしてもあると感じるケースがあります。
このような場合には、医師面談を行い、自賠責保険の後遺障害の認定基準を説明し、それが、医学的に見た後遺症とは必ずしも同一ではないことを丁寧に説明をすれば、ほとんどのケースでご理解をいただけます。医師面談をする際にも、上記のような医師側のスタンスを踏まえて、丁寧に説明を行うことがポイントです。医師としての仕事の中心は、病気やケガを治すことであり、後遺障害の診断書を作成することではありません。医師が自賠責保険の認定基準を知らなかったとしても、それは、さして不思議なことではありません。医師の仕事に敬意を持ち、患者(依頼者)にとって自賠責保険の後遺障害の認定手続の重要性をしっかりと丁寧に説明をすれば、医師面談はスムーズにいきます。
今回のケースは、医師面談により、医師の協力を得ることができ、良い結果につながった典型的なケースでした。