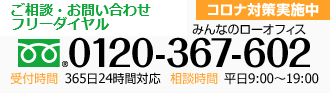交通事故の「過剰診療」に要注意!治療費打ち切り、慰謝料減額、後遺障害認定への影響と対策

最終更新日2025.9.5(公開日:2017.7.7)
監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士
音声でも解説をご用意しています。
「この治療、本当に必要なんだろうか?」「もしかして、過剰診療と疑われてしまうのではないか?」 交通事故の治療を進める中で、このような不安を感じることは決して珍しくありません。
特に、治療が長引いたり、整骨院への通院を検討したりする際に、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるのではないか、あるいは、後になって慰謝料が減額されてしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、交通事故における過剰診療とは具体的に何を指すのか、それがなぜ問題となるのか、そして、あなたが安心して適切な治療を受けながら、正当な補償を得るために何に気をつけ、どう行動すれば良いのかを、わかりやすく解説します。
あなたの疑問や不安を解消し、適切なサポートを受けるための第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
目次
交通事故における過剰診療とは?なぜ問題になるのか
交通事故による怪我の治療は、被害者の回復にとって非常に重要です。しかし、時に「過剰診療」と判断されてしまうケースがあります。ここでは、過剰診療とは何か、そしてなぜそれが問題になるのかを理解しましょう。
1. 過剰診療の定義と具体例
過剰診療とは、一言で言えば「医学的に必要性や合理性が認められない不必要な診療行為」のことです。これは、怪我の程度に見合わない治療の回数や内容、または不必要な検査などが該当します。
例えば、交通事故後に毎日のように通院を続けたり、既に症状が改善しているにもかかわらず長期にわたるリハビリを続けたりするケースなどが挙げられます。
保険会社は、こうした通院状況に対して「本当にその治療は必要だったのか?」という疑問を抱くことがあります。交通事故の損害賠償においては、「必要かつ相当な実費全額」が賠償の対象となるため、過剰診療と判断されると、治療費が全額認められない可能性があります。
2. 「高額診療」「濃厚診療」も問題となる
過剰診療とあわせて問題となるのが「高額診療」と「濃厚診療」です。高額診療とは、「診療行為に対する報酬額が、特別な理由もないのに、社会一般の診療費水準と比べて著しく高額な場合」を指します。
特に交通事故の治療で自由診療が行われる場合、医療機関が独自に診療報酬を設定できるため、一般的な水準よりも大幅に高額な費用が請求されることがあります。一方、濃厚診療は、「受傷の程度に比べて、必要以上に丁寧な診療行為」を指します。
これらの診療も、保険会社から治療の「必要性」や「相当性」がないと判断されると、支払い拒否や減額の対象となる可能性があります。特に、むちうち症のような他覚所見(レントゲンやMRIなどで客観的に確認できる症状)に乏しい怪我の場合に、治療期間が長期化すると、これらの問題が指摘されやすい傾向にあります。
「過剰診療」と疑われたらどうなる?知っておくべき3つのリスク
もしあなたが交通事故の治療で「過剰診療」と疑われてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。知っておくべき主要な3つのリスクについて解説します。
1. 治療費や慰謝料が自己負担・減額される
最も直接的なリスクは、治療費や慰謝料の支払いを拒否されたり、減額されたりすることです。保険会社が「過剰な治療だった」と判断した場合、その分の治療費は損害賠償の対象とは認められません。
たとえ相手方の保険会社が治療費を医療機関に直接支払う「一括払い」をしていたとしても、それはあくまで一時的な「内払い」や「仮払い」に過ぎません。最終的な示談交渉の際に、過剰と判断された分の金額は、賠償金全体から差し引かれ、結果的にあなたの自己負担となってしまう可能性があります。
また、慰謝料についても、通院の必要性や相当性が認められないと、その期間や回数に応じた慰謝料が減額されることがあります。例えば、通院日数が極端に少ない場合、「みなし通院期間」が適用され、本来もらえるはずの慰謝料が大幅にカットされる可能性もあります。
2. 治療費が「打ち切り」になる可能性がある
過剰診療を疑われると、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられるリスクが高まります。特に、自賠責保険が定める傷害部分の限度額120万円を超えそうになると、保険会社は治療の必要性を厳しくチェックし始める傾向があります。これは、120万円を超えた保険金の支払いは任意保険会社からの支払いとなるためです。
治療費の打ち切りを伝えられた場合、それ以降の治療費は原則として自己負担となります。もし治療を続ける必要があったとしても、立て替えた費用を後から回収するためには、裁判を起こすなど、新たな手間と費用がかかる可能性も出てきます。
また、1か月以上通院期間が空いてしまうと、治療中断と評価され、治療の因果関係が否定されて治療費の打ち切りにつながるおそれもあります。
3. 最悪の場合、詐欺罪に問われることも
最も深刻なリスクとして、意図的に治療を長引かせたり、通院日数を水増ししたりして保険金を得ようとする行為は、保険会社から「保険金不正請求」とみなされ、詐欺罪に問われる可能性があります。
日本の刑法では、人を欺いて財産を交付させた場合、「10年以下の拘禁刑」に処すると定められています(刑法第246条)。
たとえ未遂に終わったとしても、詐欺未遂罪が成立し、同様に拘禁刑が科される可能性があります。
実際に、整骨院の院長と患者が共謀して通院日数を水増しし、多額の保険金をだまし取ったとして逮捕された事例もあります。
こうした行為は、刑事罰だけでなく、保険会社から多額の損害賠償を請求されるという民事責任も負うことになります。決して「儲け話」などと安易に考えず、水増し通院の誘いには絶対に加担してはいけません。
交通事故の治療で「過剰診療」と疑われないための5つのポイント
過剰診療のリスクを避け、安心して適切な治療を受け、正当な補償を得るためには、以下のポイントを心がけることが大切です。
1. 事故直後から速やかに病院(整形外科)を受診する
交通事故に遭ったら、まずはすぐに病院を受診することが何よりも重要です。怪我の痛みは、事故直後には感じなくても、後から出てくるケースも少なくありません。事故から通院開始まで1週間程度の時間が空いてしまうと、それだけで後遺障害認定の可能性が低くなったり、保険会社から事故と怪我の因果関係を争われ、治療費の支払いを拒否されたりするリスクが高まります。
初診時には、レントゲン、CT、MRIなどの精密検査をできるだけ早い段階で受けることをおすすめします。
これらの検査結果は、あなたの怪我の状態を客観的に示す重要な証拠となり、示談交渉や後遺障害等級認定において非常に役立ちます。
2. 医師の指示に基づき、適切な頻度と期間で通院する
治療の期間や頻度は、医師の医学的判断に基づき、症状や回復の経過に合わせて調整することが不可欠です。
保険会社から正当な治療費や慰謝料の支払いを受けるためには、医師の指示に従った適切な通院を心がけましょう。
一般的に、むちうちや捻挫などの軽症の場合、1か月から3か月程度が通院期間の目安とされています。打撲であれば数週間から1か月程度です。
通院頻度については、「週3日程度」が治療効果と後遺障害認定の双方にとって最も適当な治療頻度であるといえます。
毎日通院するような過剰な頻度は、保険会社から過剰診療を疑われる原因となり、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながる可能性があります。
整骨院や接骨院に通う場合の注意点
整骨院や接骨院での施術は、痛みの緩和に効果を感じやすい方も多いため、整骨院や接骨院への通院を希望する被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定実務では、医師免許を持つ医師の治療が正当な治療と評価され、接骨院や整骨院での治療は、整形外科での治療よりも一段落ちる治療として「正当に評価されない」傾向があります。
西洋医学に基礎を置く整形外科での治療と比べ、東洋医学に基礎を置く整骨院や接骨院での治療はエビデンスが乏しいと考えられていることが背景にあります。裁判所も、整形外科での治療を第一と考えています。
そのため、接骨院や整骨院に通院する際は、以下の点に特に注意してください。
整形外科の医師の許可や同意を得る
最も望ましいのは、整形外科に通院しつつ、その医師の許可や同意を得て整骨院等での施術を併用することです。可能であれば、医師が整骨院での治療に同意していることを診断書や後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
施術部位の一致
整形外科の治療部位と整骨院等での施術部位が異なる場合、過剰診療とみなされ、施術費の支払いを拒否されます。施術部位が医師の診断部位と一致しているかを必ず確認しましょう。
整形外科への定期的な通院
整骨院だけに頼らず、整形外科にも月に1回以上は定期的に通院し、医師による経過観察を受けるようにしてください。整骨院のみの通院では、保険会社から「医師の指示や同意のない不必要な治療である」と判断され、治療費が打ち切られやすくなります。
柔道整復師や鍼灸師による施術費用は、「症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合」に認められる傾向にありますが、医師の同意は包括的なものではなく、患者を診察した上で個別具体的に行われる必要があります。もっとも裁判例では医師の指示がなくても、症状改善効果があれば賠償を認めたケースもあります(神戸地判平成23年10月5日など)。
3. 症状を正確に伝え、医療記録をきちんと残す
医師に自分の症状を正確に、具体的に伝えることが重要です。特に、事故当初から痛みを訴えていたにもかかわらず、診断書やレセプトにその症状がすぐに記載されないケースもあります。
このような場合、カルテや問診票などの医療記録を取り寄せて、あなたがどのような自覚症状を訴えていたかを調査することも有効です。
画像撮影の部位も、痛みを訴えたために医師が撮影した証拠となり、症状を最初から訴えていたことを強く裏付けられます。
通院の際には、診察券や領収書を保管するだけでなく、通院日記などをつけることで、治療内容や症状の経過を客観的に記録しておくことも有効です。
これらの医療記録は、後々保険会社との交渉や、万が一裁判になった際に、あなたの治療の必要性を証明するための重要な証拠となります。
4. 健康保険の活用も視野に入れる
交通事故の治療は自由診療で行われることが多いですが、健康保険を利用することも可能です。厚生労働省も、交通事故の治療であっても健康保険診療が受けられることを繰り返し公表しています。健康保険を利用するメリットは、治療費が高額診療と見なされて支払いを拒否されるリスクを避けられる点にあります。
ただし、健康保険を利用した場合、自賠責保険の定型用紙による診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書などを病院が書いてくれない場合があるため、事前に病院と相談しておく必要があります。
5. 水増し通院の誘いは絶対に断る
ごく稀に、整骨院などで「通院していない日も通ったことにしますね」といった水増し通院の誘いを受けることがあるようです。
実際、そのようなことをした柔道整復師が逮捕されたというようなニュースも目にします。しかし、これは断固として拒否しなければなりません。
実際に受けていない施術を受けたことにしたり、怪我をしていない部位の施術を請求したりする行為も水増し通院に該当します。
このような水増し通院に加担し、不正に保険金をだまし取ろうとすると、前述の通り詐欺罪に問われる可能性があります。
不正請求はしたが保険会社が支払いを拒否し未遂に終わった場合でも詐欺未遂罪が成立し、刑事罰だけでなく、保険会社から損害賠償請求されるなどの民事責任も負うことになります。
決して安易に考えず、きっぱりと断り、もし誘われたら速やかに他の医療機関への転院を検討しましょう。
その際は、事前に医師と保険会社に事情を話して承諾を得ておくことが大切です。
交通事故の治療費・慰謝料はどのように決まる?
交通事故の治療費や慰謝料がどのように算定されるのかを理解することは、過剰診療に関する不安を解消し、適切な補償を受ける上で非常に役立ちます。
1. 治療費の「必要性」「相当性」とは?
治療費が損害賠償の対象として認められるためには、その治療に「必要性」と「相当性」が求められます。
治療を受けることで、怪我の状態が良くなる、つまり症状の改善効果があることです。
治療の内容や通院の頻度が適切であることです。
この「必要性」と「相当性」は、単に治療を行い、治療費を支払ったという事実だけでなく、その治療が事故との因果関係があり、費用として適切であるかどうかを主張・証明する必要があります。特に、高額診療や過剰診療の場合には、この必要性・相当性が否定され、治療費が損害賠償の対象とならないことがあります。例えば、医師の裁量を超えて明らかに不必要だと判断される医療行為が行われた場合などが該当します。
2. 自由診療と健康保険診療の違い、点単価の問題
交通事故の治療は、多くの場合、健康保険を使わない「自由診療」で行われます。自由診療では、健康保険診療のような診療報酬に関する規制がないため、各医療機関が自由に報酬額を設定できます。このため、「高額診療」として問題となるのが「1点単価」です。
日本の健康保険診療では、診療行為や検査、薬剤ごとに点数が定められており、1点につき10円として報酬額が算定されます。しかし、自由診療ではこの単価に法的規制がないため、医療機関によって1点あたりの単価が異なります。過去には、1点単価が25円を超えるような高額な請求が問題となるケースもありました。
裁判例では、健康保険診療における診療報酬基準を「一応の基準」としつつ、個別事情を考慮して、これを修正すべきかどうかが判断されます。
例えば、東京地方裁判所平成元年3月14日の判決(通称「1点10円判決」)では、自由診療であっても、診療報酬額は社会通念に従った合理的なものである必要があり、健康保険診療の範囲で治療が可能な場合は、1点10円を基準とすべきとされました。
他方、福岡高等裁判所平成8年10月23日の判決では1点15円を認めた例も存在します。
近年では、多くの裁判例で1点10円を超える医療費の賠償が認められています。ただ、そのような裁判例では、1点の単価がそもそも争点とされていない場合が多いです。
横浜地方裁判所令和元年5月16日の判決では、1点12円の範囲で相当因果関係を認めつつ、保険会社が一括対応で直接支払った金額の限度で相当性を認める判断も出ています。
3. 慰謝料の計算基準と通院の影響
交通事故の慰謝料には、主に「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
これらの慰謝料を算定する際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの基準が使われます。
この3つの基準は、一般的に「自賠責基準<任意保険基準<弁護士(裁判)基準」の順で金額が高くなります。
入通院慰謝料は、治療期間や通院日数に影響を受けますが、過剰診療はここにも影響を及ぼします。自賠責基準の場合、入通院慰謝料は「1日あたりの金額4,300円 × 対象日数」で算出されます。
この「対象日数」は、「実際の治療期間(通院しなかった日も含め事故日から治療終了までの全日数)」と「実際に治療した日数(整形外科や整骨院に実際に通院した日数)×2」のどちらか短い方が採用されます。
例えば、3か月間週2回通院(実治療日数26日)した場合でも、4,300円 × (26日 × 2)= 223,600円となり、単純に3か月分の治療期間(90日)で計算されるわけではありません。また、自賠責保険の計算では、1か月あたりの通院日数の上限が15日に定められているため、それ以上通院しても慰謝料は増額しません。
一方、弁護士(裁判)基準では、治療期間が慰謝料の主要な変動要素となります。弁護士基準で計算した慰謝料額は、自賠責基準よりも大幅に高くなる傾向があります。
しかし、必要以上の通院は、保険会社から漫然治療(だらだらと意味なく治療を続けること)と判断され、入通院慰謝料や治療費を減額される可能性があります。逆に、通院頻度が少なすぎると、後遺障害等級認定で不利になったり、慰謝料が減額されたりするリスクもあります。
過剰診療の不安を感じたら、すぐに弁護士に相談を
交通事故の治療は、ただでさえ心身に負担がかかるものです。それに加えて「過剰診療」と疑われるかもしれないという不安や、実際に治療費の打ち切りを打診されるような事態に直面すると、精神的な負担は計り知れません。
もしあなたが、
- 保険会社から治療費の打ち切りを迫られている
- 「過剰診療」と指摘されて治療費や慰謝料の減額を打診されている
- 適切な治療を受けているのに、なぜか保険会社との交渉がうまくいかない
- 整骨院への通院について不安がある
- 現在の治療が本当に適切なのか、第三者の意見を聞きたい
といったお悩みをお持ちであれば、一人で抱え込まず、早めに交通事故問題に強い弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
適切なアドバイス
交通事故案件に詳しい弁護士は、あなたの怪我の状況や治療内容が過剰診療とみなされないか、法的な観点から適切に判断し、アドバイスを提供できます。
保険会社との交渉を有利に進める
弁護士があなたの代理人として保険会社と交渉することで、被害者の主張がスムーズに伝わり、治療の必要性や相当性を専門的な視点から説明できます。これにより、治療費の打ち切りや慰謝料の不当な減額を回避し、適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。
精神的な負担の軽減
複雑な交渉や法的な手続を弁護士に任せることで、あなたは治療に専念でき、精神的な負担を軽減することができます。
後遺障害認定のサポート
適切な通院や医療記録の準備は、後遺障害認定を受ける上でも非常に重要です。弁護士は、この複雑な手続もサポートし、あなたが正当な後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れるよう尽力します。
まとめ
交通事故の治療における過剰診療は、被害者の方にとって治療費の自己負担や慰謝料の減額、さらには治療の打ち切りといった大きなリスクを伴う問題です。しかし、これらのリスクは、正しい知識を持ち、適切な行動を心がけることで十分に回避できます。
大切なのは、事故直後から速やかに病院を受診し、医師の指示に従って適切な頻度と期間で通院することです。また、整骨院などを利用する際は医師の同意を得るなど、ルールを守ることが肝心です。そして、水増し通院などの不正行為には絶対に加担してはいけません。
もし、あなたが治療費や慰謝料に関する不安や疑問を感じたり、保険会社とのやり取りにストレスを感じたりした場合は、一人で悩まず、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。私たちは、あなたの正当な権利を守り、安心して治療に専念できるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。